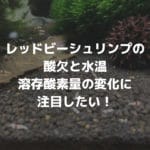どうも、元ブリーダーのurushi(urushiebi64)です。
今回は真夏の水槽の水温についての話と対策方法です。水温と言えば、真夏以外でも朝夕の気温差の激しい時期にも注意して欲しいものです。
繁殖や生死にかかわる水温を、この記事で一度確認しましょう!
レッドビーシュリンプの水槽 真夏の水温対策していますか?
地域によって違いはありますが、春~夏の終わり頃までは水槽温度が、レッドビーシュリンプには耐えられないほど上昇しやすくなるので注意が必要です。
エビは元気にしていますか?
レッドビーシュリンプにとって水温上昇は、死亡するリスクを引き上げる要因になります。水温が上がるとなぜ死亡するリスクが上がるかご存知ですか?
高水温が危険な理由
- 祖先のエビが流れのある小川に生息するため、高水温に元々適応していない
- 水中の溶存酸素量が減るため
- バクテリアをはじめ、生物が活性化し必要酸素量が増えるため
レッドビーシュリンプの祖先のエビ自体が、ディスカスのように高水温を好む種ではないということが上がられます。
さらに、水温上昇は溶存酸素の低下を招くとともに、反対に生物の必要酸素量は増えるという特徴があります。
水温上昇に注意!溶存酸素は減り、必要酸素は増える
レッドビーシュリンプのもとになったヌマエビも、自然界でも緩やかな流れのある所に住んでいます。
もともと高い水温の地域に住んでいないので、溶存酸素量とは別に考えても、ディスカスなんかとは違いレッドビーシュリは高水温自体が得意じゃありません。
さらに、水槽内の水温が上がると溶存酸素量は減り追い打ちをかけるように、バクテリア類とレッドビーシュリンプ自体の活性が上がり必要酸素量が増えます。
つまり水中の酸素量は減るのに、生体が必要とする酸素量は増える。
水温上昇で起こってくる問題の一つがレッドビーシュリンプの酸欠です。レッドビーシュリンプを含め、ヌマエビは酸欠に弱いです。
レッドビーシュリンプの水温の限界は?
結論から言うと、28℃以下をキープするのがベストです。できれば26℃以下がおすすめです。
『漆えび血統』は水草にくっついた稚エビが、知らない間に外のベランダ水槽で夏を越していたことがありました。外のベランダ水槽は殖え過ぎた水草用にしていたのですが、水温は暑い時間で30~32℃ほどでした。レッドビーシュリンプには過酷ともいえる環境だったのにもかかわらず、元気に過ごしていて秋に大きくなって見つけた次第です。
ただ、いろんなレッドビーシュリンプを見てきましたが、生きる力は血統による強さがすごく関係していて、28℃以下でもポツポツと死んでしまう血統もありました。
過保護な環境で、単純に色の濃さなど色彩だけ追い求めた近親交配が進めば、そりゃ弱くもなりますね。
いくら白や赤のべた塗り個体でも、大きく強いレッドビーシュリンプでなければ…、飼育がとても困難なものになります。その点、雑種である(最近の)シャドーシュリンプやクラウドシュリンプなんかは強いですね。(最近では残念ながら、表現だけを追い求めた弱い個体も増えてきましたが。)
レッドビーシュリンプの水温
- 基本的には、最高水温は28℃以下での飼育がオススメ。安全なのは26℃以下!
- 28℃以上になってくると死亡のリスクが高まる。
- 血統により弱い血統は28℃以下でも死亡する。強い血統は30℃近くでも元気なこともある。
- 1日の中で2℃以上の水温変化は避ける。(朝25℃で昼間28℃など。)
夏場は必須!水槽の水温上昇を防ぐアイテム
レッドビーシュリンプの水槽は、28℃以上にはならないよう(できれば26℃以下)にしてあげるのが良いです。水温管理が気温の高い時期でもできれば、夏でもバンバン稚エビは増えますよ。
水槽が多ければエアコンで部屋ごと冷やすのが一番効率的です。水槽の数が少なければ、ファンの利用がお手軽です。部屋全体がエアコン管理できない場合は、圧倒的に水槽用クーラーが最強アイテムです。
- 水槽が多い:部屋全体エアコンで管理
- 最強のアイテム:水槽用クーラー(ゼンスイ)
- お手軽:冷却ファンと逆サーモスタット
お手軽に水槽の水温を下げられる|ファン+逆サーモ
室温が28℃程度までの上昇で済むなら、冷却ファンを使えばOKです。あえてオーバースペックのものを使えば、3℃くらいは下げてくれますし、結構水温も安定します。
ファンを使う場合、忘れず一緒にセットしたいのが逆サーモです。水温が冷えすぎるのを防いでくれるので、水温が下がりすぎてレッドビーシュリンプへのダメージを与えることを抑えてくれます。
冷却ファンを使う場合は、必ず逆サーモをセットで取り付けます。
ただ、留守中や西日が当たって、室内の温度が33℃を超える時間帯があるのなら、冷却ファンだけでは苦しいです。
確実に水温管理するなら水槽用クーラー
urushiは水槽が2つまでの時は水槽用クーラーを使用していました。
部屋の温度が28℃を超えるような場合には、ファンだけでの水槽の温度管理には限界があるからです。

外部ろ過を使用する必要があったり、水槽のクーラーの熱で室内が暑くなったりしてしまう部分はありますが、60センチ水槽以上などで飼育している場合は、水槽用クーラーが水温安定には良かったです。
24時間エアコンつけっぱなしが難しい場合は、水槽用クーラーが一番良いと言えます。夏休みや旅行で出かけている間や、仕事から帰った時にレッドビーシュリンプが全滅していたら、ショックで立ち直れないと思うので。
クーラーのイチオシは圧倒的にゼンスイです。
ゼンスイの水槽用クーラーは動作音も控えめで、冷却能力と温度管理能力はピカイチです。ちなみにurushiが研究者の時に研究所でも採用していました。
テトラのモノは安くて導入しやすいのですが、クーラーと呼べるほどはパワーがありません。イメージとしてはファンとゼンスイのクーラーの間くらいです。
エアレーション強化にも取り組もう!
水温の上昇を抑えるとともに、やってもらいたい高水温時の対処がエアレーションの強化です。
これにより死亡する確率をグッと下げることができます!
レッドビーシュリンプは、酸素を体に取り込むのが下手な生き物です。ヘモグロビンを利用している人を含めた動物(赤い血を持つ)の半分の能力しかありません。それはヘモグロビンでなく、ヘモシアニンという呼吸色素を利用して酸素運搬しているからなんです。
レッドビーシュリンプのために、溶存酸素量が減る高水温時期はエアレーションを強化して、酸欠にならないようにしてあげてくださいね。
urushiのおすすめは、細かい泡が出るウッドストーンの導入です。
-

-
ビーシュリンプの酸欠と水温|溶存酸素量の変化に注目したい!
続きを見る
水槽のライトにも工夫をしよう!
夏場に熱をかなり発生させて水温を上げるものに、水槽用ライトがあります。
LEDライトでも熱をもつものも多く、冷却効果が高く熱くなりにくいライトを使うことで、水温上昇を効果的に防ぐことになります。

-

-
【コトブキ フラットLED SSレビュー】熱くなりにくい大型アルミ製ボディのLEDライト
続きを見る
注意したい日内変動の水温
最高水温上昇を抑えると同時に、水温の日内変動にも注意してください。
30℃以下をキープできていたとしても、朝の水温が25℃で日中が28℃…といったように一日で大きく水温に変動があると、レッドビーシュリンプにとってもつらい環境です。
体力のない個体から死亡したり、その時は持ちこたえてもダメージが後からきてポツポツと死んでしまうこともあります。
ヒトでも一日の気温差が大きいときは風邪をひきやすいですよね。レッドビーシュリンプは変温動物なので水温変動の影響はとても大きいので注意が必要です。
アマゾンフロッグピットなどの浮草には注意!

最後に、水槽にアマゾンフロッグピットなどの浮草を入れている場合に注意していただきたいポイントがあります。
浮草が水面を覆う面積に気を付けてください。
水の中に酸素が溶け込むには、空気と接する面積を大きくする必要があります。エアレーションすると水の中でも空気に触れますし、水面が波立つことでも空気と触れる表面積が増え酸素が溶け込みます。
しかし、浮草が水面を覆っていると、おのずと水と空気が接する面積が小さくなり、水中の溶存酸素量は減ってしまいます。とくに夏場は浮草もあっという間に育ちやすくなるので、こまめに間引いてくださいね。
レッドビーシュリンプの水温|夏場の水温上昇による死亡を防ごう!まとめ
この記事では「レッドビーシュリンプの水温|夏場の水温上昇による死亡を防ごう!」について書きました。
レッドビーシュリンプは28℃を超えるような高水温では、死亡するリスクが高まります。夏場は水温上昇を防ぐ対策が必須と言っていいと思います。
水槽の本数や、室内の温度によってエアコンで部屋全体を冷やしてしまうのか、水槽用クーラーを使うのか、冷却ファンを使うのかが変わってきます。
目安は、水温が28℃以下を保てることです。ちなみに、昼と夜の水温の差が2℃以上ないように心がけます。日中27.7℃で、夜になり人が居るからとエアコンをかけて25℃とかになってしまうと、水温の日内変動が大き過ぎるので問題です。
上手に水温をコントロールできれば、夏でも稚エビはたくさん増えますよ!
-

-
夏の暑さを活かそう!秋に向けてのレッドビーシュリンプ水槽立ち上げ
続きを見る
-

-
酸欠とシュリンプの血液の関係 オススメのエアポンプ
続きを見る
-

-
エアレーションでレッドビーシュリンプの死亡を防ぐ!
続きを見る
-

-
ビーシュリンプの酸欠と水温|溶存酸素量の変化に注目したい!
続きを見る