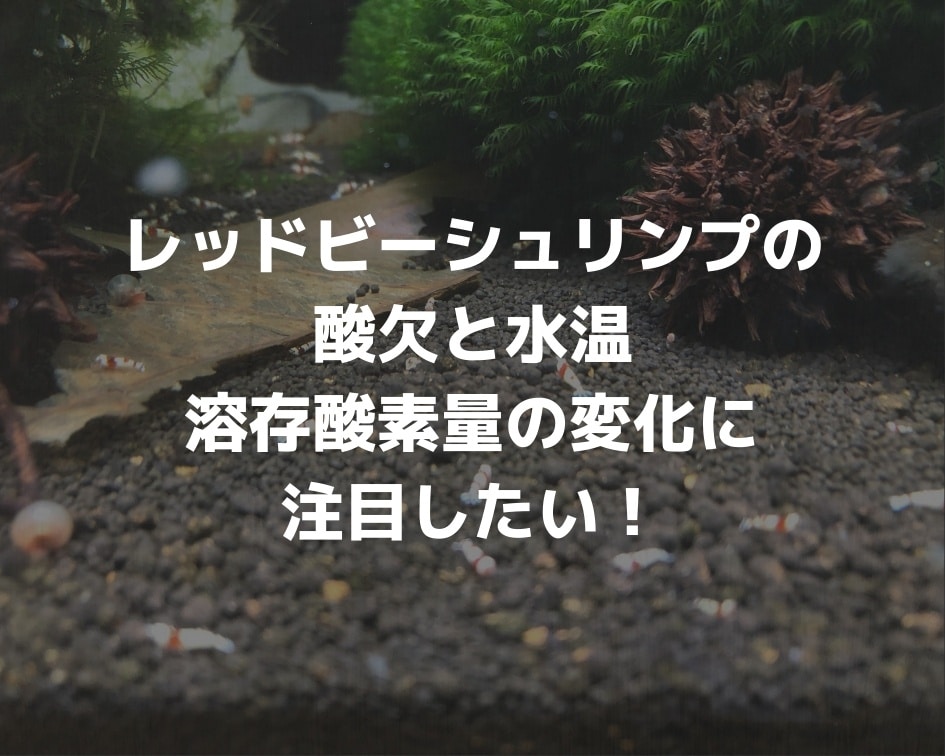どうも、元ブリーダーのurushi(urushiebi64)です。
レッドビーシュリンプは高水温に弱いといわれています。単純に水温が高いことばかり注目され、その要因の1つが酸欠というのは見落とされがちです。
この記事では、水温と水中の溶存酸素量の変化を踏まえて、レッドビーシュリンプの酸欠について説明します。
なぜビーシュリンプが酸欠に弱いのか
レッドビーシュリンプを含めシュリンプ類は、酸欠に弱いとよく言われています。確かにそれは科学的にも本当かとも考えられます。
甲殻類は青い血をしており、ヘモシアニンという血色素を使って酸素を運搬しています。ヘモシアニンはヘモグロビンと単純に比べると酸素運搬効率が悪いです。
酸素との結合
- ヘモグロビン=1:1
- ヘモシアニン=2:1
ヘモグロビンが1:1で酸素と結び付くのに対し、ヘモシアニンは2:1とヘモシアン2つに対し酸素を1つ結合します。
ヘモシアニンが単純に劣っているという話ではありません。ヘモシアニンには低い温度で働くという強みが存在します。しかし、酸素の結合はヘモグロビンの半分です。
このことが直接、レッドビーシュリンプの酸欠に結び付くと言い切れませんが、少なからず可能性はあるでしょう。
水中の溶存酸素に注目してみよう!

レッドビーシュリンプがヘモシアニンを持つということも踏まえたうえで、今回は水中の酸素の量の話をしてみたいと思います。
エアレーションがレッドビーシュリンプには良いっていうのは、一般的に知られている話ですし、urushiの記事でも度々登場しますよね。
「レッドビーシュリンプに酸素供給を!エアレーションを!」と言いますけど、実際のところって水中の溶解酸素量ってどうなんでしょう?
溶存酸素に注目して、レッドビーシュリンプの酸欠対策を考えていきたいです。
水温が上がると溶存酸素量が減る
水中の溶存酸素量の算出には計算式があります。
25℃の時の溶存酸素の計算式
0.0272×0.209×32×1000/22.2=8.11 mg/l
溶存酸素を計算すると、水温が25℃の時は1リットルに対して8.11ミリグラム酸素が溶けているということが分かります。同様に計算すると、水温が30℃になると養鱒酸素量は7.53ミリグラムに下がります。
水温と溶存酸素量の違い
- 25℃:8.11mg/L
- 30℃:7.53mg/L
8.11ミリグラムと7.53ミリグラムを比べると、数字的には少しの差に感じるかもしれませんが、溶存酸素量としてはかなりの差です。
水温が上がると酸素の溶ける量が少なくなってしまうということが分かっていただけたと思います。
水温が上がると消費される酸素量が増える
18℃から25℃に水温が上がるとレッドビーシュリンプの代謝は上がります。
18℃では繁殖しないのに、25℃になると次から次と抱卵して稚エビの数が増えます。(ただし、30℃近くの高水温になると、レッドビーシュリンプの活性は下がり死亡する個体が出ます。)
同じように水温が上昇すると、バクテリアの代謝も上がるということを忘れてはいけません。
ポイント
水温上昇=バクテリア・レッドビーシュリンプの酸素消費量UP↑
水温上昇=溶存酸素量down↓
バクテリアは目に見えませんが、結構酸素の消費は多いです。水温が上がると溶存酸素量は減るのに、バクテリアをはじめレッドビーシュリンプの酸素消費量は上がります。
水温が上がると十分にエアレーションしていない場合、酸欠が起こるのは当たり前ですね。
しかし!!
水中の酸素の量は空気中の酸素の量よりものすごく少なくて、1/33程度しかないんです。
水中で人間は生きられないですよね?水中という環境下で生きる生物がもつエラは、肺に比べてとても効率的に酸素を取り入れることが出来る優れものだと言えます。
そう考えると、urushiはエビは酸欠に弱いって考えが何だかエビに失礼な気がしてきました。「人間より、僕らは酸素取り込めるんだい」ってエビが言いそうで(笑)
レッドビーシュリンプが酸欠にならないように、エアレーションはしっかりしてあげましょう。とくに水温が上がり始める春~夏にかけては気にしたいポイントです。
-

-
酸欠とシュリンプの血液の関係 オススメのエアポンプ
続きを見る
-

-
エアレーションでレッドビーシュリンプの死亡を防ぐ!
続きを見る
-

-
レッドビーシュリンプの水温|夏場の水温上昇による死亡を防ごう!
続きを見る